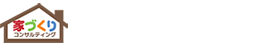住宅にまつわる税金はとても多いです。契約書に貼る印紙税から登録免許税、不動産取得税、固定資産税・・・、たくさんあります。
すべての税金を詳しく知りたい方は、家づくりお役立ち情報『住宅にまつわる税金・補助金』をご覧下さい。
ここでは失敗しやすい、そしてペナルティーの大きな税金・・・贈与税の注意点をご紹介します。親御さんから住宅資金を援助してもらう方は是非よく読んでください。
家を建てるときに親からお金をもらったら贈与税はかかるの?

「親に頼らず、自分たちだけでマイホームを考えています。」
このような立派な方は家づくり相談に来られる方の中でもかなり多いです。素晴らしいと思います。
ところが、親御さんは、「子どものためにマイホーム資金を出してあげたい!!」と考えてお金を準備しているケースも多いんです。
さて、問題です。
マイホームが完成して新築祝いで1,000万円親御さんからもらったら、贈与税はかかるでしょうか?
答えは…
- 2024年(令和6年)1月1日から2024年(令和6年)12月31日までの間にもらったマイホーム資金
- 親、祖父母(直系尊属)からの質の高い住宅の住宅取得資金の贈与
- その年の1月1日時点で18歳以上
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限は2026(令和8)年12月31日まで
- 贈与年の翌年3月15日までに住宅を取得・居住することが見込まれる(居住は遅くとも同年12月31日まで)
これらの条件を満たせば下の表の限度額の範囲で、贈与税がかからない、つまり非課税となるのです。
(他にも細かい条件がありますので、それは住宅にまつわる税金・補助金/贈与税のページをご覧ください。)
受贈者ひとりについての非課税限度額(消費税10%)
| 贈与年 | 質の高い住宅 | 左記以外 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年)1月1日~2024年(令和6年)12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
質の高い住宅とは、以下の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅家屋のことです。
- ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)
- 2023年(令和5年)12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年(令和6年)6月30日までに建築した住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免振建築物
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
親からの資金援助で家を建てる場合、税率が高い贈与税を払わずにすむなら払いたくないですよね。
住宅購入の場合には贈与税の非課税限度額があったり、また「相続時に税金の精算をしましょう」という相続時精算課税制度があったりします。
やさしいご両親からの住宅資金援助。「ムダに税金を払うことになって失敗した!」なんてことがないようにしましょうね。
どんなときに贈与税がかかるの?
下のようなケースで贈与税の可能性がでてきます。
- 子供名義で親が貯金をしていた。
- 親や祖父母からお金をもらった。
- 登記の時に、お金を出していない人の名義をいれた。
このような場合は必ず専門家に相談して下さい。びっくりするような贈与税の請求が来るかもしれません。
日本の税率で最も高い税率が贈与税です。知らなかったでは済まされない贈与税の落とし穴です。
「税務署に分からなければ大丈夫じゃないの?」
そのように思われる方もいらっしゃいます。
バレなければ結果的に贈与税を支払う必要はない(こんなこと書いても大丈夫かな?)のですが、ある手続きをしておけばびくびくする必要は全くなくなります。
国が「このようにしたら贈与税を払わなくても良いですよ!!」といってくれていることがあるので、それを上手く使えば良いだけの話です。
詳しくは、住宅にまつわる税金・補助金/贈与税のページに書いていますのでそちらをご覧ください。
土地代金の支払いと家の建築が年またぎになるときも注意
秋ごろから家づくりの検討をはじめて、年末にいい土地が見つかり、土地契約&建物の請負契約をすることになった方がいらっしゃいました。
親が援助してくれる、というので12月に振り込みをしてもらいましたが、実際に不動産屋さんや住宅メーカーに支払うのは年明けでした。
さて、贈与税非課税の特例の適用を受けるための手続きはいつすればよいでしょうか?
答えは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
ところがこの方は、不動産屋さんや住宅メーカーに支払ったのは贈与を受けた翌年だったから、住宅ローン控除の申請とともにその次の年に申請を出したのです。
この方は、税務署からの確認が届く前に気づき、持分登記の変更手続きを行いましたが、登記変更費用や税務署との相談に時間をとられるなど、余分に時間とお金を使うことになってしまいました。
家づくりの検討が年またぎになる方は、いつ資金援助を受けたのか?いつ税金が発生するのか?に注意してくださいね。
住宅にかかる税金は難しく、失敗すると余分な税金を払ってしまうことになりかねません。
心配な方はぜひ家づくりコンサルティングにご相談くださいね。→住宅購入ライフプラン診断
住宅購入時の税金を得する方法
住宅購入の税金で注意する税金に贈与税がある、ということは前項でお話いたしました。
住宅資金を援助してもらう場合、次のような方法に分かれます。
- (1)お金をもらう
- (2)お金を借りる
- (3)共有名義にする
住宅資金の援助の方法それぞれのメリット、デメリット、注意点をお伝えします。
(1)お金をもらう場合
※注意点
- 贈与税がかかる可能性あり!
- もらう金額でどの制度を利用するかを検討
1.住宅取得資金等贈与の特例
2.相続時精算課税制度
※メリット
- 相続税対策に有効
- 家計に負担はない
※デメリット
- 資金援助は頼みにくい
- ほかの兄弟姉妹との不公平感が残る
(2)お金を借りる場合
※注意点
- 「住宅ローンを組むと金利が持ったいないから親から借ります」という場合、ある時払いの催促ナシでは贈与と認定されることがある
- 借用書、返済履歴など、税務署に説明できる準備が必要
※メリット
- 贈与税の課税関係はない
- 資金援助を頼みやすい
- ほかの兄弟姉妹との不公平感がない
※デメリット
- 利息は貸主の雑所得になり所得税対象となる
- 貸借実態が厳しく問われ、贈与税認定課税の心配が残る
- 親族からの借金は住宅ローン控除対象外である
(3)共有名義にする場合
※注意点
- 親と一緒に買うということ
- 贈与税もかからず借用書も不要
※メリット
- 贈与税・所得税の課税関係はない
- 家計に負担はない
※デメリット
- 資金援助は頼みにくい
- 親の持分が相続できる保証はない
それぞれ援助の方法には一長一短があります。
住宅資金援助がある場合は、「金額はいくらか?」「どの方法で援助をしてもらうべきか?」「贈与税を払わなくて済むやり方は?」ということを考え、必ず専門家に相談したほうがいいと思います。
贈与税・相続税を始め、住宅購入にまつわる税金は法改正が多く複雑で、一般の方には非常に分かりづらいものです。
家づくりコンサルティングでは、税理士の先生と常に情報交換を行っており、住宅購入にまつわる税金について分かりやすくご説明をさせていただいています。
住宅にまつわる税金を含めて、家づくりのアドバイスを受けたい方は、家づくり相談のページをご覧ください。